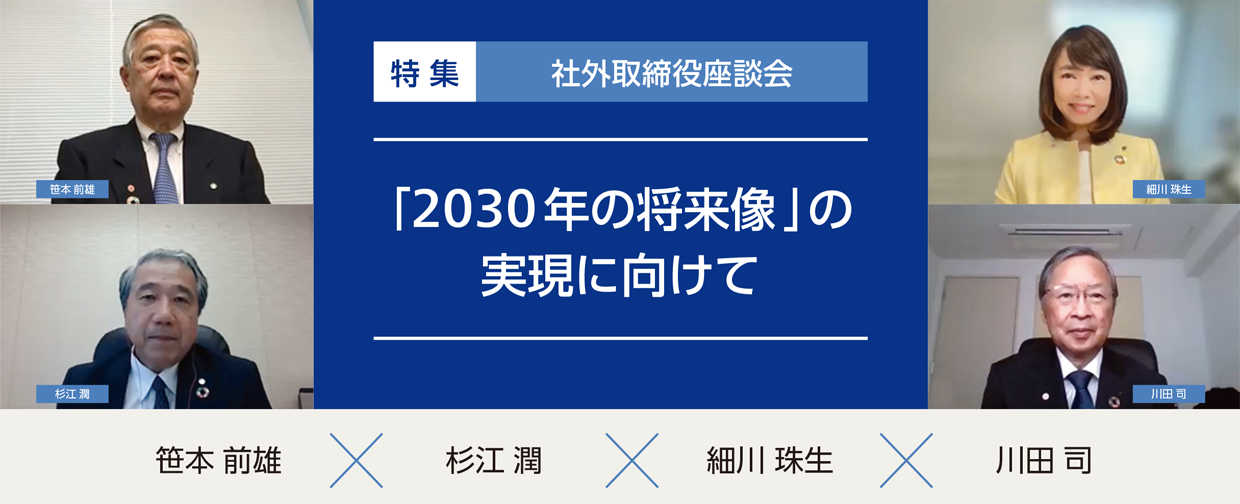
当社のコーポレートガバナンスに対する評価
笹本取締役会では、社外取締役がそれぞれ違った切り口で発言しますので、非常に活発な議論がなされています。時には「社内 対 社外」が少し鮮明になるほどに白熱する場面もあります。
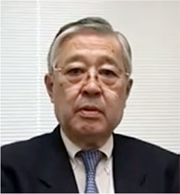
それは、当社の企業活動が非常にダイナミックで、議論を尽くし、新たなステージを常に目指しているということでもあります。私自身は、「この会社を良い会社にしたい」という一心から議論に参加しています。
私が考える「良い会社」とは、組織の風土として透明性を維持しつつ、統制の利いた、公正な判断が行われていることを意味します。従業員一人ひとりが日々の仕事にやりがいを感じ、企業としても個人としても成長が実感できているか。企業価値が向上し、株主の利益が追求されているか。これらの点についての考え方を私自身の経験を活かし申し上げています。
業務執行側の判断が透明性や公正性をポイントになされているかを、ガバナンスコードやコンプライアンス規定などに照らして検証する、そういった日々の積み重ねが企業価値の向上につながると考えています。
杉江当社のコーポレートガバナンスあるいは内部統制は大変充実していると感じています。
私は財務省で税務に長く携わっていた関係で、入社前は、建設業界はコンプライアンスがやや弱いというイメージがありました。しかし当社では、税務調査についてもその結果が取締役会に報告され、議論されています。私自身も、税務や会計の専門家としての知見、そして公務員としての経験に基づいて、しっかりと発言していきたいと考えています。
数多くの現場を抱えていると、パワハラやセクハラなどの問題が起こりがちに思われますが、当社においてはi ーメッセージ(内部通報制度)を通じてその状況が取締役会でモニタリングされています。
今、笹本さんが話されたように、取締役会では、さまざまな問題が真面目に議論されており、このような議論が会社全体のコーポレートガバナンスの質を高めていると評価しています。
川田2021年6月に就任してからこの1年の取締役会での議論は、思っていた以上に活発で、監督・モニタリング機能がかなり発揮されているとの印象を持っています。
社外取締役の役割は、独立した立場からモニタリングすることだと思いますが、この役割を遂行するうえで難しいのは、経営判断にどこまで立ち入るかという点です。ビジネスにリスクはつきもので、執行側にリスクを取ることを認めつつ、健全な企業家精神に基づいた経営を求める、そのバランスがなかなか難しいと思います。
社外取締役に対するサポートとして取締役会事務局が設置され、また、社外取締役は地方の現場視察も行っています。現場の社員は大変やりがいを持って取り組んでおり、地域住民のことも考えながら、地域にも溶け込んで仕事をしていることを大変心強く思っています。当社の力は、やはり現場だと実感しています。
細川取締役会のガバナンスには、二つのポイントがあると思っています。
一つは皆さんがお話しされているように非常に活発な議論がなされていますが、なぜ活発かといえば、社外取締役の役割が非常に大きいということだと思います。社外取締役4人の立場や考えの違いがあっても、そこから議論が発展していくことで、取締役会の活性化につながっています。その一方で、社内取締役の発言がやや少ないことが課題と認識しています。
二つ目は、ガバナンスはイコール透明性だという点です。社外取締役は、「予定調和」の中におりませんので、透明性のため、社内外的に適切に説明できるかどうかを追求するのが重要な役割であり、その事柄を適切に説明するのが社内取締役の責任であると捉えています。
中期経営計画の策定についての取締役会での議論
笹本今回の中期経営計画(中計)は、前中期経営計画を策定する際に掲げた「2030年の将来像」に則り、それに向けて3年刻みとして作成された、戦略と戦術との中間にある位置付けの中計と考えています。
取締役会では、事業計画の内容について多くの議論と詳細な検討がなされましたが、私自身が何度も申し上げたのは数字、とりわけ収益ということで、「どのくらい儲けられるのか」を繰り返し問いかけました。
これは、当社が会社としてさらに強くなる必要があるからです。自己資本の充実も「これで良し」ではなく、さらに高いところを目指さなければなりません。
議論の結果、経営計画として株主あるいはステークホルダーの皆さまにいくつかお約束をしたわけですから、これをどのように実現していくのかが肝要です。公表した中計の何倍もの、積み上げた詳細な事業計画が会社の中にあるわけですから、それらが部門ごとにどのように進捗しているかを、年々、半期ごと、四半期ごとに評価していくのが社外取締役の役割になります。
杉江笹本さんのお話のように、中計策定ではいかに収益力を上げていくかが一番の関心事でした。そして、自己資本を充実させるのか、配当を増やすのかのバランスについて非常に大きな議論になりました。
基本的に配当性向を高めていく方向になりましたが、建設業界全体も同様の方向にあり、他社とのバランスをどのようにしていくかは今後の課題といえます。自己資本を積んで競争力を上げていくという観点では、例えばM&Aも自社の競争力を高め、将来的な企業価値の創造につながります。一定の配当も必要という議論もよく分かりますので、経営者がどのように判断するかが一番大事になっていきます。

川田海外の経験が長かったため、今度の中計が海外事業に重点を置いている点に注目しています。
当社の海外事業は約700億円の売上げで、最終年度の2024年度に1,100億円、2030年度には2,000億円の目標を掲げています。この目標を達成するには、体制の整備、特に外国人人材の登用が重要です。現在、外国人正社員は50名程度ですが、海外の現場で雇用している外国人は3,000名を超えます。グローバル人材開発センターを設置して人材育成にあたっていますが、当社の将来はまさに外国人人材にかかっていると言っても過言ではありません。
もう一点、中計で注目するのが、杉江さんのお話にもあった株主還元策です。総還元性向50%程度という目標は株主を代弁する立場からは歓迎すべき目標といえます。他方、企業は中長期的な企業価値の向上を目指す必要があり、また株主だけでなく他のステークホルダーとの関係にも配慮すべき責務があります。この目標実現にあたっては複眼的な視点を持って臨まなければなりません。
細川中計の策定にあたり、各ワーキンググループに女性が参画したことを高く評価しております。お三方のお話のように収益を上げて株主や社員に適切に還元する財務体質になることが目指すべき姿であると同時に、その実現にあたっては、誰が収益を稼ぐのかという意味で、人材育成が非常に大事だと思っています。
「2030年の将来像」を長期的な目標とした中での、2回目の中期経営計画として考えるべきは、2030年とはどのような時代かということです。2030年は、昨年、中学2年生であった子どもたちが新卒で入社する年です。今の中学生の生き方や、価値観を考え、彼らに用意する社会はどのような姿かという視点で考えてほしいと申し上げてきました。母親として子育てをしている私の役割としては、自分の子どもが生きる社会はどうあるべきかを常に考える視点を盛り込んでいただくことだと考えています。
長期的な視点で当社が直面する課題とは
笹本私たちは日々、鉄骨を建て、鉄筋を組み、コンクリートを打設することで「はし」と「まち」と「ひと」に関わっています。その中で会社の将来をどのように意識するかではないでしょうか。今日の仕事、明日の仕事と同時に、5年先、10年先を常に展望し、課題認識をしなければなりません。請負業としての「限界」をいかに克服し、より「攻める会社」になり、主導的で持続的な企業になるのかをぜひ考えていってほしいと思います。
何よりも「モノをつくる会社」ですから、技術力をもっと強く意識する必要があります。「三井住友建設に頼めば」という技術を一つでも二つでも増やしていくことが、将来に向けた持続的な企業価値向上や、株主さまへの利益の還元拡大につながっていきます。
杉江川田さんのお話のように、将来を見据えた国際化が一番重要です。世界の成長エンジンである東南アジアのインフラ整備に貢献していくべきです。
そのためには外国人人材の登用以外にも、当社が持つ橋梁建設の高い技術力をさらに活用するため、シンガポールにある海洋掘削会社を買収したような現地法人へのM&Aによって、グループとしての競争力を高めていくことが欠かせません。現地法人の自由度を尊重しつつもガバナンスを利かせていく、ここでのバランスが重要であると理解しています。
川田日本経済は、今後、急激な成長が期待できないため、アジア・アフリカといった成長のポテンシャルのある海外に目を向けていく必要があります。2030年度の海外事業2,000億円は、売上高全体の約3分の1に高める計画です。このくらいの割合にもっていかなければ、当社が生き残るのも難しくなりかねません。
今まで日本経済はグローバル化と言われてきましたが、一方で空洞化が進み過ぎ、日本は今やモノづくりを考え直す時期に来ていると思います。建設業はまさにモノづくりの典型です。日本の建築の技術水準は世界的に見ても依然として高く、この技術を世界で活かしていく必要があります。三井住友建設の果たすべき役割は、まだまだ大きいと言えます。
細川2022年度、「自信と誇りを胸にお互いに尊重し合い、主体的に行動することでサステナブル社会の実現に向けた新たな成長を遂げる」という社長方針が打ち出されました。特に大事だと思うのは「お互いに尊重し合って主体的に行動する」というところです。

ダイバーシティを目指し、海外事業を強化するには、その土地のさまざまな文化や慣習、人々の生活など、そこから導き出される個々人の考えを尊重し合うことが非常に重要です。現状を見ると、もう少し現地の事情に敏感になることはもちろんのこと、国内においても、性別や年齢、国籍や地域性による違いを受け入れ、尊重し合うための努力がもっと必要だと思います。
もう一つ、技術力は非常に大事ですが、一方で人間力も重要です。米国のトップレベルの大学では文系・理系を問わず、まずリベラルアーツを学んだうえで専門分野に進んでいきます。技術をどのように活かしていくかはまさに人間力が問われるからです。
ステークホルダーのバランスをどのように図るべきか
笹本現在の中計は、株主、お客さま、従業員、地域社会などのバランスを意識して策定されています。
これを推進していくにあたっては、まず数値化して共有するという意識を持ちたいと考えています。私自身の自戒を込めて、数値化する努力というのを怠ってはいけないと強く思っています。それは数値化できない目標を共有するのは難しいと考えるからです。

杉江2030年の将来像である「新しい価値で『ひと』と『まち』をささえてつなぐグローバル建設企業」には、持続可能な社会の実現という考え方が根底にあり、これを従業員全体で共有していくことが必要です。
今回の中計はサステナビリティに重点を置いているため、取り組みだけでなく、情報開示にも取り組んでいかなければなりません。
川田中計を見ると、当社がサステナビリティを巡る問題に真正面から取り組んでいることがよく分かると思います。
私は外務省時代に人権問題を担当していましたので、人権について一言触れます。
私が人権問題を担当していた1990年代は、人権は専ら国と国との関係における問題でしたが、今やビジネスの世界で企業価値の判断基準の一つになっています。国連ではビジネスと人権に関する指導原則が採択され、日本国政府もビジネスと人権に関する行動計画を策定しています。
当社も2021年11月に「人権方針」を策定しました。これは大変歓迎すべきことで、当社が海外事業に重点を置き、グローバル企業として活躍していくうえで、大変重要な要素です。
また、今後、自然災害への対応が世界中で大きな課題になると予想されます。国内で自然災害に強い、強靭な国土づくりに貢献するのは当然ですが、そのノウハウを駆使することで、まさに世界規模で自然災害に強い国づくりに貢献できると思います。
細川就任以来、私に期待されている役割の一環として、女性従業員との懇談を積極的に取り組んできました。この3年間で、個別、集団も含めて100名近い女性と懇談し、悩みや課題など女性の声を吸い上げ、その都度経営層にフィードバックしてきました。2022年度からD&I推進部が立ち上がったことには大きな手応えを感じています。同時に、各本部の年度方針にD&Iについての方針が組み込まれたことは、今後推進していくうえで重要な一歩になります。D&Iに注目する投資家が増えているので、もう後戻りできないばかりか、積極的に推進していく施策として取り組んでいくべきです。
当社の女性は控えめな方が多いことに非常に驚きました。そのような人にも、積極的に活躍の場を提供していくのと同時に、社長方針にある「自信と誇りを持って」の「自信」をどのように持たせるかが課題と認識しています。
その一方で、「自分が役に立っている」ということを実感したい社員が非常に多くいます。男性、女性に限らず、お互いに感謝の気持ちをきちんと表すということは、モチベーションを上げるうえでも大事だと思っています。
毎日生き生きと、この仕事をやって良かったと思えるのは、制度ではなく、職場の雰囲気や人間関係というまさに風土であると思います。そのためにはもっとコミュニケーションを良くしていくことを大いに期待しています。
笹本当社はまだまだ手探りの状況で、細川さんのお話にあった、ESG投資家の支持を得るといったことが実は極めて重要になります。建設業で140年ほどの間に身に付けた意識を適切に変革するため、「自ら決めて、決めたらやる」を愚直に積み重ねていくしかないと思います。
杉江私は、上司が女性社員をしっかり活躍できるよう育てられるかどうかが一番の問題であり、女性社員をどのように導いて行けばよいのかをきちんと考えていく必要があると思っています。
川田世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数2022 で日本は146カ国中116位です。当社だけの問題ではなく、日本全体で女性の進出が遅れているわけです。ポジティブアクションを取り、具体的な数値目標を定めない限り、改善は望めないと思います。
当社も、新入社員の女性比率目標20%を掲げていますが、50%など大胆な目標にし、管理職も2割にするといったことをやらないと実態は改善していきません。
細川女性たちにも「特別待遇」されることに躊躇する思いはありますが、意識的に女性を登用していくことが必要です。例えば、女性部長は現在3名ですが、中計の最終年度の目標は8名です。比率は5.0%で、2019年の従業員100名以上の企業平均である6.9%にも満たないという実態です。それでもこの目標を確実に守っていくことが重要であり、そのためには真剣な姿勢と覚悟が何より必要です。
全員本日は、ありがとうございました。
