![]()
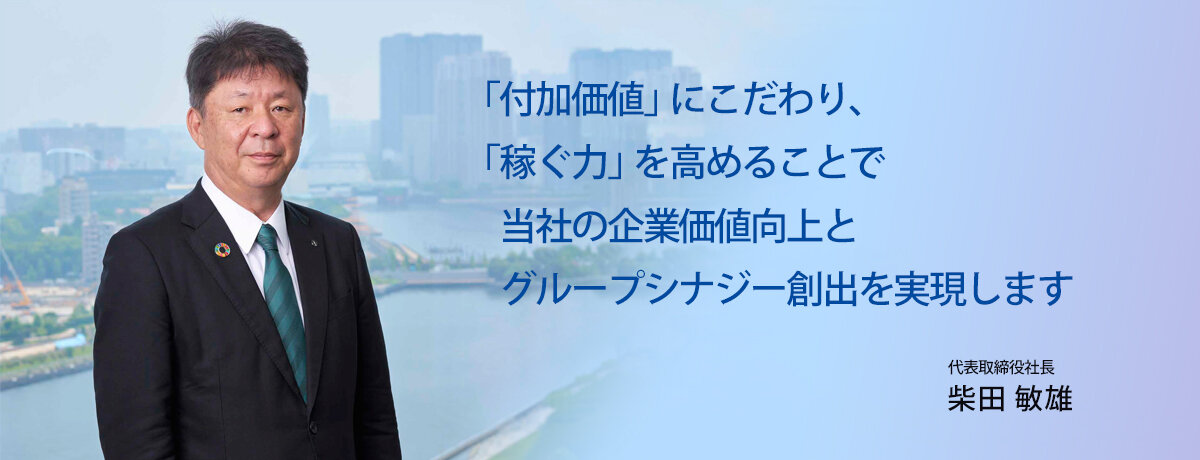
建設業界の構造的課題が深刻化する中で
2025年3月期決算は若干ながら黒字に転換
2024年度について、まず外部環境としては、建設業が抱える構造的な課題が深刻化した1年でした。建設資材は世界的なエネルギーや資源の価格上昇を受けて高止まりの状態です。労務費を含め建設コストが上昇し、この状況は当面続くと考えられます。
また、労務の需給逼迫の問題も顕在化しています。建設現場で働く技能労働者の高齢化と若手の減少が加速してきました。さらに昨年度は、大都市圏の再開発や地方の半導体工場・データセンターなど大型の建設プロジェクトに技能労働者が集中し、全国的な労務不足に輪をかけました。働き方改革は、国の指導もあってかなり進展してきていますが、その半面、労務費の上昇や人的リソース不足などの問題も深刻化しています。建設業を魅力ある産業として復活させるには、労働条件の改善に加えて実態に合わせた賃金アップが不可欠で、これについては国の施策や民間の発注者の皆さまのご理解に期待するところです。
昨年度の当社の状況に関してですが、まず多額の工事損失が発生した国内大型建築工事については、ステークホルダーの皆さまに大変ご心配をおかけしております。昨年9月に上棟した後、2025年8月の本体工事竣工、10月末引渡しに向けて工程どおりに進捗しています。この工事は、当社が得意とする超高層住宅でのエラーでしたが、体制を立て直して以降、日本一の高さとなるこの超高層住宅の完成に向け全社を挙げて対応してきました。当社の急速施工技術により最短3日でワンフロアずつ躯体を構築して最後までやり遂げたこと、また工事の過程でさまざまな新技術を開発・実装できたことは、携わった社員にも会社にも大きな財産と自信になりました。今回の教訓を糧に、今後も案件を見極めながら、超高層住宅への取り組みは継続していきたいと考えています。
2025年3月期決算については、中間決算の時点で、上述の国内大型建築工事の損失計上により通期では赤字になるという見通しを発表しましたが、その後の半年間に土木事業と海外事業の業績が大きく好転したことと、建築事業でも他の工事の採算がかなり改善したことから、最終的には若干ながら黒字転換することができました。外的な要因として為替の影響もありますが、内的な要因としては、私が社長になって1年数カ月訴えてきた「現場への回帰」という方針が社内に浸透し、各事業部門が採算を改善してきた結果であると実感しています。国内大型建築工事の損失を受けて、受注プロセス強化、採算重視の営業方針、取り組み段階からのフロントローディングなど、さまざまな対策を行ってきました。今後も業務改善に取り組み、収益力向上等を目指します。
「収益力の向上」「成長分野への挑戦」「人材(=人財)基盤の強化」 それぞれの取り組みが一定の成果を挙げた3年間
2024年度を最終年度とする「中期経営計画2022-2024」では、「収益力の向上」「成長分野への挑戦」「人材(=人財)基盤の強化」という3つのテーマを掲げて取り組んできました。
まず「収益力の向上」については、国内大型建築工事が大きな損失を出したことで全体の数字は目標未達となりましたが、国内の土木事業で強みのPC橋梁・大規模更新工事やトンネルを軸に、2023年度に過去最高益を達成するなど、順調に推移しました。建築事業では、採算を重視した受注と手持ち工事の消化により良質な案件へと手持ち工事の入れ替えが進み、受注時利益率も、足元の国内大型建築工事を除くと7%を超えるまで改善してきました。
2つ目のテーマである「成長分野への挑戦」は、残念ながら、ここ数年の業績悪化に伴い、技術開発など諸々の成長投資が限定的になってしまいました。一方、成長分野の旗振り役である海外事業は2023年度に事業規模を1,000億円まで拡大でき、成果が挙がったといえます。また、サステナブル社会の実現を目指す水上太陽光発電事業も、まだ小規模ながら着実に進化してきました。現在、発電容量は17.3MWとなっています。

最後に「人材(=人財)基盤の強化」について、まずは「D&Iポリシー」を策定し、その定着に向けた教育・ワークショップ活動を実施しました。また、海外大学出身の外国籍人材を当社正社員として採用したり、グローバルな人材開発センターであるHDC(Human Resources Development Center)を複数のグローバル拠点で立ち上げ、教育に取り組んだりしました。
残った課題として最も大きいのは、人材の問題です。特に当社では、30代後半から40代前半の人員が非常に少ない、いびつな人員構成になっており、ベテラン社員から若手へとバトンを引き継ぐための時間があまり残されていないことが喫緊の課題です。
直面する諸課題の解決と、毀損した資本の早期回復のため
インフロニア・ホールディングスとの経営統合を決断
今回、インフロニア・ホールディングスとの経営統合に至った背景をお伝えします。近年、当社が直面してきた課題として、建設業界に共通する担い手不足、建設資機材価格の高止まり、労務需給の逼迫といった構造的課題に加えて、国内大型建築工事での損失により大きく毀損した資本の早期回復、早期の企業価値向上という当社固有の課題がありました。単独で存続してこれらの課題に取り組むことも検討しましたが、特に毀損した資本の回復には、現状のまま利益が出続けたとしても7~8年はかかってしまう計算になります。そうした点を考慮した結果、インフロニア・ホールディングスとの経営統合によるシナジー効果で中長期的に事業基盤を拡大し、より確実でスピーディーな企業価値向上を図るのが最善であるとの判断に至ったのです。
インフロニアグループは現在、「請負」と「脱請負」それぞれの市場でビジネスを展開する「総合インフラサービス企業」を目指すことをグループ戦略としています。「脱請負」というのは、単に何かを作ることだけではなく、PPP事業や再生可能エネルギー事業を含めた、投資から運営、EXITまでのプロジェクトの全スコープをカバーすることを意味し、例えば道路・空港などのコンセッションと官民連携、アリーナやスタジアムの運営、発電事業等を指します。国内の公共事業、インフラの維持更新事業など「請負」も堅調に推移しているとはいえ、長期的に見れば人口減少などもあって新規の公共工事への投資はおそらく減少し、競争が激化していくでしょう。その中で勝ち残っていくためには、設計から施工管理、安全管理まで全体をマネジメントする「エンジニアリング力」が重要であり、その点で当社のポテンシャルを高く評価していただいて、今回、インフロニア・ホールディングスから経営統合のオファーがあったのだと認識しています。当社としても、その期待に十分応えて力を発揮できると考えています。当社は現状では「請負」がベースになりますが、インフロニアグループの一員として長期的には「脱請負」の分野も担っていくことになると考えています。
統合後も経営方針や成長戦略は継続し、
グループのシナジー効果を活かした成長を加速

インフロニアグループに経営統合した後も、当社単体としての経営方針や成長戦略を大きく転換しようとは考えていません。これまで培ってきた「請負」の領域で、統合のメリットを活かして成長の加速を目指します。
統合によるシナジー効果として最も大きいのは、インフロニアグループの中核企業である前田建設工業と当社を合わせて建設事業の事業規模がこれまでの2倍くらいになる、そのスケールメリットです。スーパーゼネコンに次ぐ規模になりますから、資材調達のコストダウンや協力会社の融通など、現業部門での大きなメリットが期待できます。
事業別でいえば、まず土木事業の面では、当社がPC橋梁や大規模更新工事に強みを持つのに対して、前田建設工業はダムなどの電力土木や防衛などに強みがありますから、全体としては補完性の高い組み合わせといえます。1つの持株会社の傘下に当社規模のゼネコンが2社ぶらさがるという形は、たぶんこれまでに例のない試みですが、そうすることで、トンネル・橋梁・河川・上下水道など土木事業分野に川上から川下までフルラインナップで対応できるようになります。インフロニアグループが推進しているインフラ運営事業も含めると、業界で唯一の立ち位置になると考えています。
建築事業では、受注ポートフォリオに似通った部分もありますが、それぞれ顧客ネットワークを持っていて、すみ分けはなされていると捉えています。超高層住宅は当社も前田建設工業も得意としており、デベロッパーを中心とした発注者は一部重複するものの、現状の旺盛な住宅需要と供給側の逼迫を考えると、あまり競争する環境ではなく、重複によるディスシナジーは限定的と見ています。当社は超高層住宅で豊富な実績を持っており、プレキャスト工法などの技術ノウハウを共有することで、インフロニアグループ全体として圧倒的な業界シェアを確保することも可能です。
海外事業については、前田建設工業が現状ではあまり進出していない一方で、当社は東南アジア・南アジアを中心に、土木ではODAを中心としたインフラ事業、建築では日系企業の工場などを中心に展開しています。経営統合後は、当社のアジアを中心とした業界トップクラスの実績とネットワークに、インフロニアグループのインフラサービスの技術ノウハウを展開することができ、将来的には海外でのPPPやPFIといった事業領域拡大の可能性も十分にあります。当社は海外事業の拡大を目指していますので、今回の経営統合がその加速につながると期待しています。
中長期的な成長に向けた方向性を見極めつつ「付加価値」にこだわり、「稼ぐ力」を高める
当社が中長期的に成長していくために、現在想定している方向性としては、次の5つが挙げられます。
1つ目は国内の公共投資。全体としては将来的に減少が見込まれますが、災害に対する予防保全の観点から国土強靭化の予算は継続的についていくと考えています。
2つ目は安全保障部門です。この先、国内でも防衛予算は増えていくと思われますが、それとともに米軍関係の工事にも注目しています。米軍がオセアニア地域で防衛拠点のインフラ整備を計画していますが、当社はグアムでの米軍案件の実績もありますので、今後注視していきたいと思います。
3つ目のカーボンニュートラルについては、先般公表された「第7次エネルギー基本計画」で再生可能エネルギーや原子力などの脱炭素電源の活用が謳われました。トランジション(エネルギー転換)の手段として挙げられる水素やアンモニア対応の設備投資が比較的早い時期に活性化すると見込まれますが、そこでは当社の低温タンクの設計施工の実績が活かせることから、既に営業活動も進めています。また、フランスで実績のある企業と協働でコンクリート製の浮体式洋上風力発電のフィジビリティスタディも進めています。
以上は主に土木分野ですが、建築分野では4つ目として、AI技術の普及に伴うデータセンターや半導体工場の建設需要が、継続的に増えると想定しています。どちらも特殊性のある建物で、規模もさまざまですから、当社としてどのような領域を狙っていくべきか、社内で議論しているところです。
最後に、海外事業としては、当社が取り組んできた東南アジアを中心とするODAのインフラ事業の需要がまだ5~10年くらいは続くと考えられます。その先については、例えばアジア開発銀行などODA以外の発注者からのインフラ事業や、先ほども述べたPPPやPFIなどの領域にインフロニアグループとして進出すべく、情報収集や研究にも取り組みます。
以上のような方向性を見据えつつ、将来的な成長に向けて、〈「付加価値」にこだわり、「稼ぐ力」を高める〉ことに注力していきます。そして、そのための重点戦略として、国内の土木・建築を中心とする「コア事業の深耕」と、海外や新規周辺領域を含む「成長事業の拡大」を図るとともに、人材戦略や技術戦略などを通じた「成長を実現する基盤の強化」に取り組んでいく考えです。
人的資本強化を目指し「人材開発本部」を新設
人事制度の抜本的な見直しも
人的資本強化には、先の中期経営計画で掲げた「人材(=人財)基盤の強化」に引き続き注力していきます。従来は管理本部の下に人事部があり、採用や評価などを担っていましたが、残念ながら人材戦略といったところまでは手が回っていませんでした。また、人材に関する部署がほかにも社内に点在していました。そうした状況を改善するため、2025年4月に「人材開発本部」を新設して人事機能を一元化するとともに、事業部門からの人員シフトにより事業戦略と連動した人材戦略の推進体制を強化しました。
人材開発本部の大きなミッションとして、人事制度の抜本的な見直しがあります。1つには、年功序列色の強い人事制度を廃して、責任の重さと権限の大きさに応じた処遇をする制度への転換を準備しており、今期中には導入する予定です。また、キャリア採用に力を入れる一環として「リファラル採用・アルムナイ採用」を制度化したり、社員の強い意見を受けて人事評価に「360度評価」を導入したりといった施策も、2025年度から行っています。さらに、多様な人材が活躍できる環境の構築を目指して、女性活躍推進にも引き続き力を入れています。女性総合職比率や女性管理職比率のKPIを設定して取り組んでいるほか、当社プロパーの女性役員の登用に向けた議論も進めています。
サステナビリティ経営については、お客さまや社員、地域などステークホルダーの皆さまに当社事業に関わり続けたいと思っていただきながら、環境・社会・経済のバランスを保って持続的な発展を図ることが重要と考えています。事業活動の中で特に社会的なインパクトが大きい課題の解決に向けた全社的な取り組みを継続しており、中でもカーボンニュートラルに関しては、グループ全体で気候変動への取り組みをさらに加速させるため、2021年に策定した「2050年カーボンニュートラルに向けたロードマップ」を2025年5月に改訂しました。「ネイチャーポジティブ」「サーキュラーエコノミー」「人権」といった重要な社会課題の解決と合わせて、ガバナンス体制などサステナビリティ経営を推進する基盤の強化も図っています。
社員と向き合い、リテンションを図りながら
経営統合をやりきるのが社長としてのミッション
当社のステークホルダーのうち、お客さまに対しては、経営統合で当社の財務基盤が安定することをご説明し、前向きなご理解をいただいています。また、唯一の株主となるインフロニア・ホールディングスに対しては、業績目標をしっかり達成することでグループ全体の企業価値向上に努めます。そのように考えていくと、経営統合に向けて今私が重視すべき最大のステークホルダーは社員であり、その社員の不安を払拭して、モチベーション向上を図ることが最優先であると思われます。今回の統合の件については、私を含めた取締役で手分けして全国の拠点へ説明に赴き、社員と直接話をしました。最初は動揺している人も多かったですし、今もまだ全員が腹落ちしているとは思いませんが、前向きな議論ができる空気になってきた手応えは感じています。これからのインフロニア・ホールディングスとの協議の経過をできるだけ社員にも共有して、意見を聞き、施策に反映していきたいと考えています。
当社はインフロニアグループの一員となる予定ですが、その後も法人格は維持され、前田建設工業とは兄弟会社として対等の精神で、基本的には単独でこれまでと変わりのない事業を継続していきます。グループ全体のシステムやルールなどは合わせていくことになるものの、当社がこれまでに培ってきた文化や風土までグループに合わせることは特段求められていません。私はむしろ、異文化どうしの接点の中からイノベーションが起こることを期待しています。大きな変化の時ではありますが、社員一人ひとりがやりがいを持って業務に取り組める環境を整えるとともに、グループとしてのシナジーを創出しながら、三井住友建設の企業価値向上を図っていく──。これが私のミッションであると強く認識し、全力で取り組んでいきます。
|
2025年9月 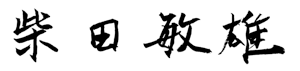 |
 |
